
若手技術者座談会の報告
国土総合研究機構 次世代ビジネス研究会
国土総合研究機構(建設技術研究所(CTI)、日本工営(NK)、パシフィックコンサルタンツ(PCKK)3社で組織)の次世代ビジネス研究会では、建設コンサルタントの魅力向上について検討しています。平成21年1月には「魅力アップに向けて」の行動方針を策定し公表しました。このたび3社の2,3年目の若い技術者と中堅の技術者に参加いただいて座談会を開催して、建設コンサルタントへの入社の動機や魅力、夢、目指すべき方向などについて語っていただきました。
| 座談会概要 | ||||||||||||||
| 開催日時 | : | 平成21年 7月21日(火)14:00〜17:30 | ||||||||||||
| 開催場所 | : | 日本工営(株) 本社3階 A 会議室 | ||||||||||||
| テーマ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 司会進行 | : | 礒部猛也委員 | ||||||||||||
| 傍聴者(敬称略) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第1部 入社2〜3年目技術者による座談会 テーマ:入社して感じたことと自分の夢
| 入社2〜3年目技術者(所属)と勤続年数 | |||
| 小池 麻里 | (CTI東京本社水工部) | 2年 | |
| 江副 拓良 | (同 東京本社社会システム部資源循環室) | 2年 | |
| 大和 賢弘 | (NK 社会システム事業部都市・地域計画部) | 1年 | |
| 寺本 雅子 | (同 流域・都市事業部地盤環境部) | 1年 | |
| 鶴見 悠史 | (PCKK 環境事業本部資源・環境部) | 2年 | |
| 渡邊 哲也 | (同 交通技術本部空港部) | 2年 | |
配付資料:行動方針 [PDF]
あいさつ
| 小松世話役 |  われわれ次世代ビジネス研究会では、「建設コンサルタントは魅力がある」と思っていますが、そのことが社会に伝わっていないということに問題意識をもってセミナーを開いたり、「魅力アップの向上」の行動方針をつくって公表するなどいろいろ試みてきました。 われわれ次世代ビジネス研究会では、「建設コンサルタントは魅力がある」と思っていますが、そのことが社会に伝わっていないということに問題意識をもってセミナーを開いたり、「魅力アップの向上」の行動方針をつくって公表するなどいろいろ試みてきました。建設3紙と議論するなかで、「建設コンサルタントはいいことをやっているのだからもっと自信と誇りをもってやっていくことが何よりも大切」じゃないかと思うようになりました。 そこで3社の社員の皆さんがどう考えて仕事をしているのかを是非聞いてみようということで座談会の開催に至りました。座談会の結果を学生へのPRなどの参考にしていきたいと思っておりますので、ざっくばらんにお話してください。 |
1.自己紹介
| 小池 | 大学では構造研究室でコンクリートの研究をしていました。水工部では河川構造物の設計や耐震調査の仕事をしています。 |
| 大和 | 大学では土木工学科で都市計画を学びました。主な業務としては、県の都市計画マスタープランの作成等があります。 |
| 渡邊 | 大学では構造、耐震を勉強しました。現在空港部に所属しています。 |
| 江副 | 大学では下水処理を勉強していましたので下水道室を希望したのですが、意に反して廃棄物業務をやっています。 |
| 寺本 |  大学では構造研究室でコンクリートの研究をしていました。水工部では河川構造物の設計や耐震調査の仕事をしています。 大学では構造研究室でコンクリートの研究をしていました。水工部では河川構造物の設計や耐震調査の仕事をしています。 |
| 鶴見 | 農学部の出身で廃棄物業務をやっています。 |
2.建設コンサルタントになろうとした動機
| 自然に興味、環境の仕事がしたい。建設コンサルタントのイメージは先輩から。(鶴見) | |||
| 父親が建設コンサルタント。先輩の話にやりがいがある業界かと思った。(江副) | |||
| 知恵やノウハウを武器にする建設コンサルタントに魅力。(大和) | |||
| 自分で設計した橋梁をみんなに利用して欲しい。(小池) | |||
| 父親の大好きな橋梁を設計したい。(渡邊) | |||
| 自分の意思が反映できる仕事と思い建設コンサルタントに。(寺本) | |||
| 鶴見 | 自然が好きで大学では環境を学び、環境に関する仕事がしたかったのです。研究室にPCKKの方が博士号を取りに来ていたので建設コンサルタントのイメージがありました。 | ||
| 江副 | 父が建設コンサルタント業界にいるので業務内容をおおよそ知っていました。就職先としてゼネコンと役所と建設コンサルタントを考えましたが、建設コンサルタントの先輩の説明会での話し方の感じが良くて、忙しいけど楽しそうに話をしていて、やりがいがある業界かなと思ったのです。 | ||
| 大和 |  大学で学んだ都市計画に携わる仕事がしたいと考えており、公務員と比べ、自らの手で計画作成ができる建設コンサルタントを選びました。慕っていた先輩から「公務員は向かない」と言われたことも大きかったです。また、ゼネコンは人の知恵よりも機材等を使うイメージが強く、一方で建設コンサルタントは自らの知恵やノウハウが武器といった点に魅力を感じました。 大学で学んだ都市計画に携わる仕事がしたいと考えており、公務員と比べ、自らの手で計画作成ができる建設コンサルタントを選びました。慕っていた先輩から「公務員は向かない」と言われたことも大きかったです。また、ゼネコンは人の知恵よりも機材等を使うイメージが強く、一方で建設コンサルタントは自らの知恵やノウハウが武器といった点に魅力を感じました。 | ||
| 小池 | 橋梁をつくりたいと思っていまして、ゼネコンでは設計部への配属が難しいと聞いていて、建設コンサルタントだと企画・設計ができるだろうと思って決めました。それに自分で設計したものをみんなに利用して欲しいと思いました。 | ||
| 渡邊 | 父が大きな橋が好きで、四国の連絡橋を見る機会がありました。将来は橋をつくってみたいと思いましたが、先輩の話によるとゼネコンで設計できる人は一握りの人で設計に携われるようになるには5〜10年かかるとのことでした。公務員は事務方の感じが強いので、設計するなら建設コンサルタントだと思っていました。就職活動時に橋梁メーカーの不祥事があったのと、PCKKの会社説明がアットホームの感じがあったので決めました。 | ||
| 寺本 | 博士になったのですが職業としてのリアリティがなく、物をつくって利益をあげるのは嫌いで、また役所へ就職した友達が疲れている感じで、たぶん自分の主張が通りにくいのかなと思いました。自分が成し遂げたいことがあるときにその意思が反映できる仕事ではないかと思い建設コンサルタントに就職しました。 | ||
3.入社して感じたこと(良かった点、悪かった点、入社前とのギャップ等)
| 発言できるまでには3〜5年かかる。技術を活かす対話が重要。(寺本) | |||
| 父親が建設コンサルタント。先輩の話にやりがいがある業界かと思った。(江副) | |||
| 自分のやりたいことができるが、忙しすぎる。ユーザーと顧客との間で立場が難しい(鶴見) | |||
| 自ら設計したものを目の当たりにするとやりがいを感じる。(江副) | |||
| 専門知識以外に社会情勢や環境面の知識が必要で、大学時代の勉強では足りない。(小池) | |||
| 技術士などの資格保有者が多いのは大手コンサルタントの魅力。(大和) | |||
| 寺本 | まだまだ思い通りにできず自分自身に対するギャップがあります。発言できるようになるまでには3〜5年かかると思っています。建設コンサルタントは、「技術が武器」だと思っていましたが、会社の人事の人に「挨拶が大事」と言われてびっくりしました。しかし、仕事を進めていくうえでは対話が大事で、技術を活かす土台になるのがきちっと対話ができることだということに気づきました。 | ||
| 鶴見 | 良かった点 仕事は「思っていたより自分のやりたかったことができる」し、大学時代に自分で気づいていないところで「やってみると面白かった」ことができるところです。 悪かった点 聞いていましたがやはり忙しいです。また、就職活動のときも考えていて今も良くわかっていない点があります。それは建設コンサルタントは公益性が高いと思っていましたが、エンドユーザーとお客さんが求めている結果が違ったときの対応は、今でも自分の中ではっきりしません。お客さんの意向で提案や報告書の内容を変えないといけない場合があります。 | ||
| 渡邊 | 良かった点 思っていたより残業が少ない点です。 悪かった点 私が所属している空港部は設計と計画をやりますが、私は計算で答えがでる設計が好きですが、計画は設計と比べてあいまいな点が多く、何となくあやふやでギャップを感じます。 | ||
| 江副 | 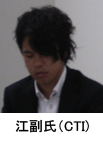 良かった点 会社説明会で「設計したものができあがるのを目の当たりにした時にやりがいを感じる」と若手社員が答えているのを聞いて偉そうにと思っていましたが、入社して1年目に小さいものですが図面を描いて数ヵ月後に出来上がったのを見て感動しました。ギャップとは違いますが、これが「やりがい」だと思いました。 良かった点 会社説明会で「設計したものができあがるのを目の当たりにした時にやりがいを感じる」と若手社員が答えているのを聞いて偉そうにと思っていましたが、入社して1年目に小さいものですが図面を描いて数ヵ月後に出来上がったのを見て感動しました。ギャップとは違いますが、これが「やりがい」だと思いました。悪かった点 残業が多い点です。仕事に楽しさを見つける余裕がまだないですが、楽しさを見つけてこそ一人前だと思っています。 | ||
| 小池 | 良かった点 もっと残業が多いと思っていましたが、結構「飲みニケーション」や、「スポーツ大会」など仕事以外の行事もあって、コミュニケーションの場があることです。 悪かった点 大学時代の勉強だけでは足りないと思いました。構造物の設計には専門の知識以外に社会情勢や環境面の勉強も必要です。 | ||
| 大和 | 良かった点 学生時代にすごい資格だと思っていた技術士や一級建築士を多くの先輩が普通に持っており、職場環境のレベルが高いと感じます。自分の技術者としてのレベル向上が期待できて、これは大手コンサルタントの魅力だと思います。 悪かった点 発注者ともう少し対等だと思っていましたが、結構発注者の言いなりで、建設コンサルタントの自由度や発言力がない感じがしています。 | ||
 | |||
4. 今仕事をしていて楽しいこと、将来したいこと、夢は
| 最終処分場を設計したい。(江副) | |||
| クライアントへ提案して、それが採用されたい。(寺本) | |||
| 業務が社会貢献に繋がり、社会がその公益性の高さを知って味方になってほしい。(鶴見) | |||
| 土木の楽しさを次世代の子供に知ってもらい味方になってもらいたい。(小池) | |||
| 「大和がいなかったら変わらなかった」といわれるところを何箇所かつくりたい。(大和) | |||
| 海外の空港を計画、設計したい。(渡邊) | |||
| 江副 | 今は、業務を消化するのに精一杯で楽しくはありません。やりがいは、自分で設計したものを目の当たりにすることで、夢は最終処分場を設計することです。そのためには必要な道路や電気の知識を身につけて戦える技術者になる必要があります。 | ||
| 寺本 | 楽しいことは現場でボーリング作業員と話をしたり、調査業務で分析結果がでてくる瞬間です。業務はまだ受動的なので楽しいことはありませんが、たぶんクライアントへ提案できるようになって、それが採用されるようになると楽しくなると思います。 | ||
| 鶴見 | 楽しいことは「プロポーザル作成時」や「業務成果の納品時」の瞬間です。業務の実施中はつらく感じることが多いです。夢は、我々の業務が社会的な貢献になり、その公益性の高さを社会に認めてもらうことです。 | ||
| 小池 | 楽しいことはプロジェクトで異分野の話が聞けて視野が広がることです。夢は、全てを管理できるシビルエンジニアになることと、次世代の子供に土木や河川構造物の楽しさを知って味方になってもらうことです。 | ||
| 大和 | 都市計画の仕事ができていること自体が楽しく、特に、行政よりも住民目線の計画づくりをしているときが楽しいです。夢は、日本に多く存在するさびれた町や集落のどこかを「大和がいなかったら変わらなかった」と言われるような計画で立て直すことです。 | ||
| 渡邊 | 空港は希少価値の高い業務ですので、現場調査で「制限区域内」に入れること自体がやりがいであり、楽しさです。それとバスターミナルの計画で私と上司と発注者の提案の中で私の案が採用されたことです。夢は、海外の空港を計画、設計することです。 | ||
5.フリーディスカッション
(1)座談会の感想
| 小池 | 普段計画系の技術者の話を聞くことが無いので参考になりました。 |
| 大和 | 座談会のテーマへの答えが似通っている場合と、残業時間のように答えがバラバラだったりして、また自分が思っていたこととも違ったりしておもしろく聞けました。 |
| 寺本 |  就職理由やギャップは、お互い納得できたと思いますが、何にやりがいを覚えるとか、仕事にどのくらい重きを置くとかは、だんだん考えが分かれてくるのだと思いました。何をやりたいかを自覚すると変わってくるのだと思います。 就職理由やギャップは、お互い納得できたと思いますが、何にやりがいを覚えるとか、仕事にどのくらい重きを置くとかは、だんだん考えが分かれてくるのだと思いました。何をやりたいかを自覚すると変わってくるのだと思います。 |
(2)公共事業が縮小傾向にありますが、海外チャレンジについて
| 人口減少、高齢化など日本の課題に立ち向かいたい。それが海外への展開に役立つはず。(大和) | |||
| チャンスがあれば途上国に限らず最先端のところへも技術者として出て行きたい。(鶴見) | |||
| 環境面における日本の支援が必要。海外の土壌汚染をなくすため是非海外へ行きたい。(寺本) | |||
| 長寿命下に配慮した新設施設をつくるため、技術を蓄えてから海外へ行きたい。(小池) | |||
| 日本の空港設計は終盤を迎えており、海外へ行くしかない。(渡邊) | |||
| 海外に興味はないが、機会があれば海外に行って自分を成長させたい。(江副) | |||
| 大和 | 英語が不得意なのでなかなか前向きに考えられませんが、これから日本が直面していく人口減少、高齢化などの問題は、発展途上国でも将来きっと直面するでしょうから、まずは日本がこの課題に真剣に立ち向えば、数十年後に海外でのビジネスに繋がるかと思います。 | ||
| 鶴見 |  学生の時は海外へのあこがれを持っていました。長い目で見ると海外のその地域の人自身が建物をつくって、メンテナンスして、お金も地域の中で回るのがあるべき姿だと思います。業界としてどうすべきかについては考えがまとまっていません。 学生の時は海外へのあこがれを持っていました。長い目で見ると海外のその地域の人自身が建物をつくって、メンテナンスして、お金も地域の中で回るのがあるべき姿だと思います。業界としてどうすべきかについては考えがまとまっていません。チャンスがあれば途上国に限らず最先端のところへ技術者として出て行きたいです。 | ||
| 寺本 | 是非海外へ行きたいです。海外でも土壌汚染があるのでなくしていきたいと思っています。日本はもうモノをつくらず、海外の必要なところにつくるべきです。日本は、発展途上国へ対して日本での特に環境面からの経験を踏まえて支援すべきだと思います。 | ||
| 小池 | 技術を蓄えてから海外へ行きたいと思います。メンテナンスが重視されつつあり、新しい物をつくることが少なくなってきていますので、発展途上国において新しいものを一から、もちろん長寿命に配慮して施設をつくっていきたいと思います。 | ||
| 渡邊 | 海外へ行きたいです。空港の設計は茨城県の空港が最後と言われておりますので、海外に出て行くしかないのが現状です。 | ||
| 江副 | 今のところ海外には興味がありませんが、会社の指示があれば、新しい局面は自分が成長するチャンスだと思っていますので行きます。 | ||
(3)どうやって技術を身につけていくのか、あるいはこんな環境をつくってほしいとか?
| 自分で勉強するのは大事だが、OJTで先輩が教えてくれるのはわかり易い。(江副) | |||
| 忙しくてもモチベーションが高ければ吸収できるので、OJTで十分。(鶴見) | |||
| OJTは重要だが、小規模な業務を任せてくれれば知識も責任感もつく。(小池) | |||
| 物事を突き詰めて考えるなど仕事への心掛けと自分から進んで質問することが重要。(渡邊) | |||
| 長寿命下に配慮した新設施設をつくるため、技術を蓄えてから海外へ行きたい。(小池) | |||
| OJTは大事だが、先輩や上司との相性も重要。3年程度で変更できるとよいかも。(寺本) | |||
| 新人卒業として小規模業務を任せて欲しい。自分の成長のために使える時間が有効では。(大和) | |||
| 江副 | 一人で勉強するのが苦手でOJTで先輩が教えてくれるのはわかり易いです。自分で勉強するのは大事だとは思いますが。 | ||
| 鶴見 | OJTで十分だと思います。ただ、学ぶ方のモチベーションが低いと吸収できません。モチベーションが低いと上司の言われたとおり報告書を作成することになったりしてあまり身に付かないと思います。忙しくてもモチベーションを高く保つ工夫が必要だと思います。 | ||
| 小池 |  OJTは重要です。中堅技術者に付いて2〜3年は仕事を教えてほしいです。OJTに加えて構造設計の特徴かもしれませんが「小規模な詳細設計」を1件納品まで任せていただければ、知識も責任感もつくと思います。 OJTは重要です。中堅技術者に付いて2〜3年は仕事を教えてほしいです。OJTに加えて構造設計の特徴かもしれませんが「小規模な詳細設計」を1件納品まで任せていただければ、知識も責任感もつくと思います。 | ||
| 渡邊 | 自分の仕事への心掛けが大事で、怒られた仕事はよく覚えていて理解度が高いと思います。そういう動機付けも必要でしょう。2つ目は自分から進んで質問することです。私は、なぜこの計算式を使うのかを突き詰めながら仕事をしています。 | ||
| 寺本 | OJTは大事ですが、先輩や上司とウマが合うか否かが重要で、変更する機会があるとよいと思います。例えば、一通り習った3年後くらいに変更することでモチベーションも高まるかと思います。 | ||
| 大和 | 小さくてよいので自分が主体となる“新入社員卒業業務”みたいなものがあるとよいと思います。「この業務は安いがお前のための業務」だと新人用に受注してもらえれば嬉しいです。また、業務時間の数パーセントを自己投資の時間に使える制度がある会社では、社員の成長が早いと上司に教えてもらいました。 | ||
(4)「やりがい」をもって仕事をやっていくために、「やりがい」をみつけるために「こういう仕事をやりたい」とか、「自分はこうなります」など
| 小池 | 技術士になって、早く一人でまかせられる技術者になりたいです。 | ||||||||
| 大和 | 若いうちは「2009年は○○をやる」とエクセルに具体的に整理しチェックしながら勉強しています。将来は、主体性をもって業務を任せられる技術者になりたいです。 | ||||||||
| 渡邊 |  30歳までに技術士になって、「PCKKに渡邊がいる」と言われたいです。 30歳までに技術士になって、「PCKKに渡邊がいる」と言われたいです。 | ||||||||
| 江副 | 発注者から「また江副に頼みたい」と言われたいです。 | ||||||||
| 寺本 | なるべく自分が客観的に見られるようになって、最終的にNKでなく「寺本さん」と言われたいです。 | ||||||||
| 鶴見 | 仕事面では一人のコンサルタントの鶴見と認められるようになって、生活面でも全力で謳歌して仕事と生活をバランスさせていきたいと思っています。 | ||||||||
| 講評:高木委員 | |||||||||
 皆さんそれぞれの個性が出ていて、まず純粋さを感じました。私は30年前に漠然と入社したのですが、皆さんは建設コンサルタントの印象を事前調査されて入社しているので、初歩的なギャップは私ほどにはなかったかと思います。 皆さんそれぞれの個性が出ていて、まず純粋さを感じました。私は30年前に漠然と入社したのですが、皆さんは建設コンサルタントの印象を事前調査されて入社しているので、初歩的なギャップは私ほどにはなかったかと思います。皆さんはクライアントと市民とのギャップを感じているようですが、次世代ビジネス研究会でも同じように感じており、このギャップをなくすべく精力的に情報発信していきたいと思っています。 楽しさというものは、当たり前のことをやっていては楽しくありません。自分が思ったことと違うなと感じて、何かの拍子にわかってできたときに感動が生まれる、そんな感動が連続するような仕事のやり方をしてほしいと思います。 夢にはいろいろあると思いますが「こうなりたい」の気持ち(モチベーション)を常にもって下さい。建設コンサルタントはやりがいのある職業です。是非とも「クライアントから名前がでる技術者」になって下さい。 | |||||||||
| 座談会後の感想 | |||||||||
| 座談会終了後に参加者に感想文を提出いただいたところ、今後の検討に参考となる指摘がありましたので、主な点を以下に挙げます。 | |||||||||
| |||||||||
第2部 30歳代の中堅技術者による座談会 テーマ:私の考える建設コンサルタントが目指す新たな展開
| 中堅技術者(所属)と勤続年数 | |||
| 相良 純子 | (CTI 東京本社水システム部) | 5年 | |
| 泉 倫光 | (同 東京本社ダム部) | 13年 | |
| 柳本 諭 | (NK 流域・都市事業部上下水道部) | 11年 | |
| 秋山 成央 | (同 社会システム事業部統合情報技術部) | 11年 | |
| 戸谷 康二郎 | (PCKK 社会政策本部行政マネジメント部) | 14年 | |
| 梶井 公美子 | (同 環境事業本部環境部) | 15年 | |
| 配付資料 | : | 行動方針 [PDF] | |
| 図1 「多機能型コンサルタント」としての新たな事業展開の方向 [PDF] | |||
| 図2 新たな事業展開へのロードマップ [PDF] |
1.自己紹介
| 梶井 | 学生時代にたまたま地理学教室で地形にかかわり現地調査などをしているうちに自然環境、環境問題に興味を持つようになって、自然環境に関わる仕事がしたいという動機で建設コンサルタントを選びました。 |
| 柳本 | 大学で河川を専攻していて先生や研究室に来ていた人の助言があってNKに就職することになりました。 |
| 泉 | 入社時にダム部に配属が決まった際には、「ダムはつくらないのでは」と思っていましたが、今はまだまだ沢山やることがあって、おもしろいと思っています。 |
| 戸谷 | 道路の設計をしていて、「これからは維持管理の時代だ」ということで新設された保全システム部へ移り、3年前に行政マネジメント部に改称されました。 |
| 秋山 | NKの研究所でアルバイトをしていてそのまま入社しました。大学の研究で覚えた情報系の技術が活用できるところとして情報部署を希望しました。 |
| 相良 | 大学、大学院とも海外で過ごし、環境コンサルティング、水関係の国際会議の事務局を経て入社しました。 |
2.新しい事業展開へのロードマップ(RM)についての感想
| 「現状」に「コンサルタント個人としてこうなりたい」という意見があるとよい。(戸谷) | |||
| 少子高齢化が気がかり。地域密着型の技術者配置も必要。(秋山) | |||
| 若手は積極的に海外へ出て行くべき。コンサルタントが携わる具体的イメージ像が必要。(相良) | |||
| 抽象的業務が多くなっているが、ビックプロジェクトを遂行できる技術力が重要。(柳本) | |||
| 「多機能型コンサルタント」になれるのか、自分とのギャップを感じる。(泉) | |||
| 多機能型の方向はわかる。具体的な業務の掘り起こし方が重要。自分達の役目か。(梶井) | |||
| 戸谷 | 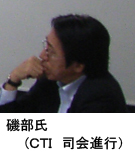 「現状」(図1)のところは、学生へもPRするなら「建設コンサルタント個人としてどうなりたいか」など個人レベルでの意見があるとわかりやすいと思います。例えば問題点としては、設計などの専門技術を持っていても一般的には目立たず、どうしても事業者である役所しか着目されない。建設コンサルタントのなかでもコーディネートする人の方が目立ち、技術を持つ人が報われず、成果が対外的に評価されにくいのが課題です。建設コンサルタントとしての方向はこれで結構かと思います。 「現状」(図1)のところは、学生へもPRするなら「建設コンサルタント個人としてどうなりたいか」など個人レベルでの意見があるとわかりやすいと思います。例えば問題点としては、設計などの専門技術を持っていても一般的には目立たず、どうしても事業者である役所しか着目されない。建設コンサルタントのなかでもコーディネートする人の方が目立ち、技術を持つ人が報われず、成果が対外的に評価されにくいのが課題です。建設コンサルタントとしての方向はこれで結構かと思います。 | ||
| 秋山 | 私は少子高齢化が気になっています。道州制の導入(図2の外部環境)とありますが、今後は地域密着型の技術者配置をしないと効率的な行政サービスができないと思います。特に安い事業費で高いサービスを提供するには飛行機を使っている場合ではありません。われわれも一緒に税金の無駄遣いをすることがないように注意が必要です。 | ||
| 相良 | RM作成の次にコンサルタントがどう携わっていくかの具体的イメージ像を考える必要があります。今後は海外へ従来と違う形で積極的に出て行くべきだと考えます。水関係ですとこれまで国際貢献とビジネスは分けて考えられていましたが、今後の世界市場はこれまでは儲からないと考えられていた地域が大半となると思われます。これからは、国際貢献となりかつ企業にとってビジネスにもなり得る総合的なビジネススキームを展開していくことが必要であり、その中で建設コンサルタントが果たしていく役割は大きいと思います。例えば、サービスやオペレーションを重視した事業を、複数の企業や研究機関、自治体などと共同で展開するといった内容が、「コンサルティングサービスの拡大」や「新たな企業形態の展開」の中で考えられます。 | ||
| 柳本 |  事業環境が難しい上、プロポーザルが増え、全体的に抽象的な業務が多くなってます。会社はそんな業務へ人的配置してきています。 事業環境が難しい上、プロポーザルが増え、全体的に抽象的な業務が多くなってます。会社はそんな業務へ人的配置してきています。今後3社が本来やるべきビックプロジェクトが何年後かに出てきても技術的にうまく遂行できるか不安です。事業スキームに「技術力の強化(先端技術・・・)」とありますが、その辺の記述がありません。一方で私自身も、10年後の自分に不安を感じています。もう1点。昨年、東南アジアで昔の高度成長期の日本の姿を彷彿とさせる土木プロジェクトを見る機会がありましたが、是非若手にも海外へ出て行く機会を与えるべきです。 | ||
| 泉 |  目指す「多機能コンサルタント」(三角形の図)の内容が多岐にわたっており、自分とのギャップが大きい感じがします。社内を見ても「できるのかな」と思います。仕事のやり方を、職人肌タイプと八方美人タイプに分けると、多機能型コンサルタントの内容は後者のタイプに見えます。職人肌の人には「刀を抜く」チャンスが無く、もったいない感じがします。「実力があるのでこのRMを描いている」のか、「RMをつくったので実力をつけろ」なのかがわかりません。 目指す「多機能コンサルタント」(三角形の図)の内容が多岐にわたっており、自分とのギャップが大きい感じがします。社内を見ても「できるのかな」と思います。仕事のやり方を、職人肌タイプと八方美人タイプに分けると、多機能型コンサルタントの内容は後者のタイプに見えます。職人肌の人には「刀を抜く」チャンスが無く、もったいない感じがします。「実力があるのでこのRMを描いている」のか、「RMをつくったので実力をつけろ」なのかがわかりません。「コンサルティングサービスの拡大」に興味があります。われわれは技術力で商売していますが、結局クライアントとの「交渉」で業務を受注しており、交渉というやりとりのサービスを使って違う方向へ展開できると考えています。 「事業領域の拡大」については、限られた市場の中のパイを取り合うことから脱却するということで「拡大」という方向性が打ち出されていると推測します。そういう意味では「教育」へのアプローチができれば子供が大きくなって「土木」への理解が進むとすれば、子供教育が我々のPRに繋がると思います。 | ||
| 梶井 | 「多機能コンサルタント」の3つの方向は、我々が今後関わっていくであろうことに関連するキーワードが入っていると思います。次には具体的にどういう業務の掘り起こし方がありうるかを見たくなりますが、自分達がその答えを出す役目かもしれません。環境分野の場合、「コンサルティングサービスの拡大」というところで「交渉」というキーワードが出ましたが、コンサルタントとしては「合意形成」をうまく支援していく役割が重要で、そのプロが必要と考えています。また、海外事業という点では、地球温暖化の分野においては、国内外に境目を設ける意味はなく、日本が培った技術開発やシステムをいかにしてアジアへ普及していくのかという点で貢献できると思います。 | ||
| 司会 | 皆さんの印象は、「RMにはいろいろ書いてあり、間違ってはいないが今ひとつピンとこない」ということでしょうか。 | ||
3.自分が考える建設コンサルタントの目指す新たな展開として、個人より3社として何をすべきか?
| 事業を促進する役割などソフト面の参画によるメリットを示すべき。海外の視点も重要。(相良) | |||
| 事業執行マネージャとして、ファイナンスの視点(事業資金の視点)が必要。(秋山) | |||
| 特に自治体では、インフラ整備の優先性を提案する統合的なマネジメントが必要。(戸谷) | |||
| 大手コンサルタントは、地方の予算化・調整・データベース化に向けた情報共有が重要。(柳本) | |||
| ハードの計画・設計技術を基にサービスの付加価値を上げる分野横断的な連携が必要。(梶井) | |||
| 維持管理までを含めた事業の資金調達が重要。(泉) | |||
| 相良 |  複数の企業や研究機関等による共同事業体に多機能コンサルタントとして参画することで、例えば海外事業展開に伴うリスクの低減や合意形成の円滑化といった場面でのファシリテーターやコーディネーターとしての役割を担っていくことができると思います。 複数の企業や研究機関等による共同事業体に多機能コンサルタントとして参画することで、例えば海外事業展開に伴うリスクの低減や合意形成の円滑化といった場面でのファシリテーターやコーディネーターとしての役割を担っていくことができると思います。RMのプラスアルファの情報としては、建設コンサルタントが新規分野にサービスを拡大することによって、他の主体や利害関係者および住民に対してどのようなメリットを提供できるのかを具体的に書き込めると、説得力を増すと思います。 | ||
| 秋山 | 建設コンサルタントが担っている事業分野は、国交省の事業ではある分野に偏っておりますが、県や二次・三次官庁ではもっと広い分野でお金のバランスをとる視点が必要になります。「多機能コンサルタント」は広い範囲をカバーすることになり、「事業執行マネージャ」として、事業スキームとしてファイナンスの視点(事業資金の視点)が必要になります。少子高齢化では、看護士の事例のような海外からの人材の国内への活用の視点も必要です。 | ||
| 戸谷 |  秋山さんの言う通りで、国交省の各部局は専門コンサルタントで対応できるかもしれませんが、自治体では例えば財務局が先導してそれぞれのインフラが今後50年でいくらかかるかを把握して予算を設定しようとしているとこもあります。異なる施設でどちらを優先するのか、どの順番で金を投資していくのかなどをどのような指標で検討していくかの統合的なマネジメントが必要で、それは3社のような多様な技術者を抱えるコンサルタントでないと提案することは難しいかもしれません。 秋山さんの言う通りで、国交省の各部局は専門コンサルタントで対応できるかもしれませんが、自治体では例えば財務局が先導してそれぞれのインフラが今後50年でいくらかかるかを把握して予算を設定しようとしているとこもあります。異なる施設でどちらを優先するのか、どの順番で金を投資していくのかなどをどのような指標で検討していくかの統合的なマネジメントが必要で、それは3社のような多様な技術者を抱えるコンサルタントでないと提案することは難しいかもしれません。 | ||
| 司会 | それで今後食べていけますか? | ||
| 戸谷 | 例えば、道路の分野でも橋、道路、舗装、附属施設のどれを優先するのかの選択には判断を支援するための提案など総合技術が求められ、その可能性はあると思います。 | ||
| 柳本 | 地域密着型の話が出ましたが、地方分権が進むと地方の専門的な業務は地方の専門のコンサルタントが受注し、大手は各地方の調整、情報の集約のデータベース化とか、予算化の話、ハード面では耐震基準も自治体が設定する方向にあるので、ファイナンシャルの話やスペックを決めるところで携わるのかなと思います。そこで全国展開している3社が情報を共有し(守秘義務の問題があるが)、駆使していく生き方があります。 | ||
| 梶井 | RMでは、インフラと社会サービスがあり、安全安心、福祉、環境などの分野がありますが、この業界は現状ではハードの計画と設計が主体です。財源が厳しい中、最小のお金の掛け方で最大の効果が得られる、社会が満足するサービスを提供する必要があり、今まで以上に分野間の連携が重要です。そのような企画の立案、運営、地元との合意形成などの事業が有望ではないかと考えます。例えば、地球温暖化の影響にインフラを対応させるには、更新時などを上手く捉え、多様な付加価値(安全安心、福祉など)を持たせる等の視点が必要になるといわれています。分野横断的なノウハウ(1つのものに多くの機能を付加する)が求められると思います。 | ||
| 泉 | 私は見積り時、人工を入れる時が楽しく、やりがいを感じます。県の橋や道路に予算を使う話をしているが結局は税金であり私はその資金の調達をやってみたいです。「コンサルティングサービスの拡大」の中の「事業をプロデュース」を私はそう理解しました。維持管理まで含めてやることで皆さんに事業への参画をアピールし、資金調達していきたいです。施設の完成後の説明をして税金以外で金を集める形態を考えていくべきです。 | ||
 | |||
4.優秀な人が集まってくる方法、学生を呼び込むPR手法は?
| 自己実現できる業界、やりがいがある仕事、人材に投資している業種などを強調すべき。(戸谷) | |||
| 作った個人が社会的に認知されることが必要。「建設コンサルタント」の名称変更も。(相良) | |||
| メディアに出る有名人が必要。募集時に「スペシャリスト」「ゼネラリスト」の区別も。(秋山) | |||
| インターネットなどメディアへのPRが必要。大学へ出向いた説明も重要。(梶井) | |||
| 高校や小学校へのPRも重要。(柳本) | |||
| 戸谷 | 「自己実現できる会社、業界である」ことのPR、「仕事だけでなく充実した生活が確保できる(残業は多いがやりがいがあるとか)」、「仕事しつつ人材にも投資している業種である」などをすることが効果的だと思います。 | ||
| 相良 | 建設コンサルタントの大半は、社会貢献に意義を感じていますが、その成果は社会的に認知されていません。つくったものには我々の名前(個人名や会社名)を積極的に出していくべきですし、それが社会へのPRにもなります。また、「建設コンサルタント」という名称は、実態を表していません。名称変更もアピールの一つの方法です。 | ||
| 秋山 |  建設コンサルタント業界の何人かがメディアに出るとか、本を書くなりして有名人がいるとPRになります。募集時に「スペシャリスト」と「ゼネラリスト」のコースを示すと将来の道筋が見えて安心するかもしれません。 建設コンサルタント業界の何人かがメディアに出るとか、本を書くなりして有名人がいるとPRになります。募集時に「スペシャリスト」と「ゼネラリスト」のコースを示すと将来の道筋が見えて安心するかもしれません。 | ||
| 梶井 | メディアやインターネットを活用して積極的にPRすべきだと思います。相良さんと同感ですが「建設コンサルタント」という名称には違和感を持っています。業界に優秀な人に来てもらうには、働いている我々自身が魅力的に映ることがまず第一で、やりがいをもってやれる仕事であること、こういう良さがあるということを、定期的に大学へ出向いて伝える機会等も持てると良いと思います。 | ||
| 柳本 | 大学のほか、土木工学を専攻したいと思わせるためにも、もっと若年層を対象として高校生や小学生へのPRも必要です。家族へのPRとして私は休日に小2の子供を浄水場へ連れていったりしています。 | ||
5.フリーディスカッション
| (1)「真の技術力」「真の総合技術力」が身に付く方法とか、理想とか | |||
| 協力会社も高齢化しており、若い技術者を教育する体制ができていない。(柳本) | |||
| 代替案を発注者と確認しながら進めていく「立ち止まる技術」が重要。(泉) | |||
| 個々人が他部門連携の視点を持ち、情報交換することが重要。(梶井) | |||
| 社会情勢をにらんだ価値観を持ち、技術者を良い方向へ向かわせる指導者が必要。(秋山) | |||
| 柳本 | 昔は協力会社とかゼネコンからの情報があふれ出るほど多く、上の人も忙しいのか結構任せてくれて、学べる機会が多かったと思います。1件業務を任せてとの要望があったが丸投げできず、どうしても我慢できずに口を出してしまいます。協力会社も高齢化してきていて、2〜3年目の若い技術者に教える体制ができていません。 | ||
| 泉 | 私の考えている技術力というのは、「立ち止まる技術」で右か左かを考え抜いて身につけるものです。正解はなく、常に代替案があってそれを発注者と確認しながら進めていくのが本当の技術力だと思います。土木技術者には感性が重要であり、安全か否かは、多分感覚だと思います。経験の中から本当の技術力がでてきます。 | ||
| 梶井 |  真の総合技術力という点では、他の部門と日常業務の中で密に連携をとることが重要と考えています。例えば、温暖化に対応したまちづくりなどに関しても、まちづくり、交通系、施設系の部署の専門家が集まって議論すると、様々なアイディアが出てくるので、他部門との情報交換の重要性を痛感しています。個々人が他部門連携の視点を持つことが重要です。 真の総合技術力という点では、他の部門と日常業務の中で密に連携をとることが重要と考えています。例えば、温暖化に対応したまちづくりなどに関しても、まちづくり、交通系、施設系の部署の専門家が集まって議論すると、様々なアイディアが出てくるので、他部門との情報交換の重要性を痛感しています。個々人が他部門連携の視点を持つことが重要です。 | ||
| 秋山 | 3社はカリスマ的な人たちが設立しましたが、社会情勢をにらみ今何が大事かを言える価値観がないと、良い技術があっても良い方向へもっていけません。良い技術を下から積上げていってもそれをどっちの方向に技術を使うのかを言いきれる人、技術者を良い方向へ向わせる人が必要です。 | ||
6.本日の感想を!
| 相良 | 建設コンサルタントという職業を改めて考えました。また、皆さんのいろんな意見を聞けた貴重な機会でした。 | ||||||||||||
| 秋山 | 座談会は世代ごとでなく、出席者全員でディスカッションするやり方もあります。総合的な技術力の話をすると、民意や住民目線は良いこともありますが、国民全体が間違った方向へいくこともありますので、それを建設コンサルタントが本来行くべき方向へ引っ張っていけると良いと思います。政府やマスコミが国民へ迎合しすぎている感じがします | ||||||||||||
| 戸谷 | RMを3社でアピールしていくのが使命だと思います。座談会はテーマが広すぎたように感じました。RMを国・発注者、業界、学生の誰に向って説明するのかで重点が異なり議論しやすくなると思うので、テーマを絞って座談会をやると良いと思います。 | ||||||||||||
| 泉 | 建設コンサルタントは知的創造性を発揮すべきだと思っていますが今日は全く発揮できず、胡散臭い感じだけがでてしまいました。まずは家族へ「建設コンサルタントのサービス」を説明していきたいです。 | ||||||||||||
| 柳本 | 会社ではこれからどうしていくかの会議が多いですが、各社でも同じだと思いました。10年前は、我々の年代で「家族を大事にしよう」などは多分言ってなかったと思います。今後会社でも生活の面でも敏感になっていきたいです。 | ||||||||||||
| 梶井 | 今回のテーマは大変難しかったです。今気づいたのですがRMと言いながら、「事業展開」と「事業スキームの充実・強化」の線が2010年から2020年まで同じ内容なのが気になります。当面2〜3年の主体別の行動計画が必要ではないでしょうか。私は、上司からよく「コンサルタントは医者や弁護士と同じ」と言われてきましたが、その意識で顧客と対等に仕事をしていくことは可能だと思います。その姿勢を後輩にも見せていくことが重要と考えています。 | ||||||||||||
| 講評:吉田委員 | |||||||||||||
 経験を踏まえた活発な議論をありがとうございました。建設コンセルタントの向かう方向に、事業のプロデュースやファイナンス、合意形成の話が出ていましたが、その重要性はそのとおりですが、一方で、海外への認識が少しうすいように感じました。 経験を踏まえた活発な議論をありがとうございました。建設コンセルタントの向かう方向に、事業のプロデュースやファイナンス、合意形成の話が出ていましたが、その重要性はそのとおりですが、一方で、海外への認識が少しうすいように感じました。社会資本整備には生活基盤と産業基盤がありますが、産業基盤の部分で海外の市場と深くつながっています。このロードマップを、誰に配るかといった視点で捉えることも重要です。 また、技術者は、縦軸に給与をとり横軸に年令をとるとS字カーブで表されます。若いうちは会社が投資している段階であり、中堅になると刈り取りの段階で、熟年になると個人としての生産性は低下するが複数の人を使って業務をするので組織としての平均生産性を上げることは可能です。 他社の話を聞く機会はあまりありませんが、今日は、皆さんが同じような考えを持ち、年代ごと、立場ごとに悩みがあることを実感しました。 | |||||||||||||
| 座談会後の感想 | |||||||||||||
| 座談会後に感想文を提出いただいたところ、今後の検討に参考となる指摘がありましたので、主な点を以下に挙げます。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
以上
